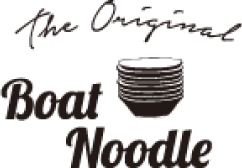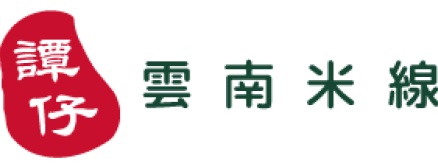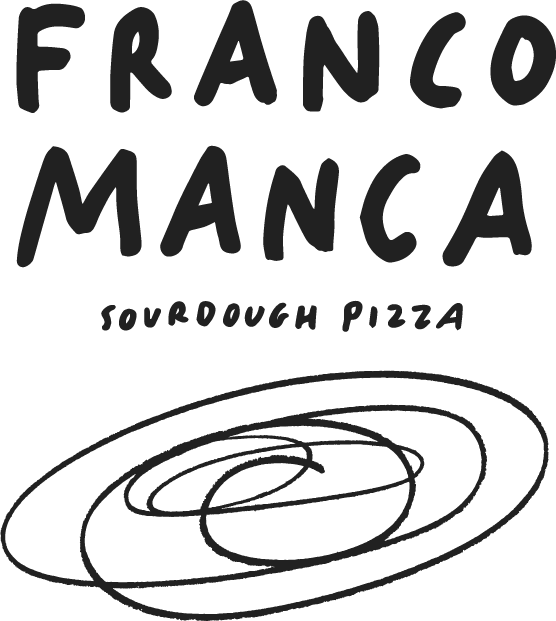◆PROFILE
森麻美 2022年1月入社
ハピネス・ヒューマンサポート本部 KANDO Creators大学 次長
兼 トレーニングマテリアル課 課長
中央大学 総合政策学部卒
大学を卒業後、スターバックス コーヒー ジャパンに入社。店長として勤務した後、当時日本で3名しかいなかったコーヒースペシャリストとしてコーヒーの教育を担当。その後、商社でコーヒー豆の輸入、海外コーヒーブランドの日本一号店の立ち上げに参加するなど、食に関する様々なビジネスに参加。トリドールホールディングスでは海外ブランドや店舗におけるフードセーフティに関する管理や教育などを担当し、新たに設立されたKANDO Creators大学でトレーニングプログラムの作成や社員向け研修の企画や管理を行っている。
◆chapter 1
興味がなかった飲食の世界。
偶然の出会いが私の運命を大きく変えました。
興味がなかった飲食の世界。
偶然の出会いが私の運命を大きく変えました。
・前職も飲食業界にいらっしゃいましたが、もともと興味があったのでしょうか。
いえ、もともと大学では比較文化論を学んでいましたし、就職活動の第一志望も文具業界でした。飲食業界に進もうとはあまり考えてなかったのですが、たまたま大学で行われていた会社説明会にスターバックス社の採用担当者が参加されていて、なんとなくエントリーしてみたところ、選考過程で嘘偽りなく正直に話ができたことが好印象となり、もしかしたら自分に合うのはこっちかな?と思うようになったのです。第一志望の会社からも内定をいただいていたのですが、結果的にスターバックス社への入社を決めました。
最初は店舗配属となりまして、アルバイトスタッフたちと接客や店舗運営などの業務を行っていました。店長となったのち、新店舗の立ち上げやドライブスルー店舗を経験しました。若手社員やアルバイトスタッフとお客様に接しながら、みんなの成長を間近で感じられる。そのことにやりがいを覚えるようになりました。最後の3年間は本社でコーヒーについての知識や愛情をどのようにお客様にお伝えしたらよいかを全国の店舗スタッフに啓発していく教育業務に携わったのですが、コーヒーだけではなく飲食そのものや人の育成に関する興味もさらに深くなっていきましたね。

・その後も飲食業界でキャリアを研鑽していったのでしょうか。
スターバックス社を退社した時に次のキャリアを考えた際、「少し冒険してみよう」と思って違う業態であるコーヒーの輸入専門商社へ転職。中南米のコーヒー畑に直接足を運び、生豆を買い付ける仕事に携わりました。そこでの経験が大きなやりがいとなりまして、その後もサンフランシスコのコーヒーブランドの日本上陸に関わったり、製菓のスタートアップで品質管理部門の立ち上げに加わったりと、食に関する様々な仕事に携わってきました。
ただ、自分のキャリアを選択するにあたっては、今もそうですが「飲食であること」は特別大きなウェイトを占めていません。店舗ならば商品が売れる、製造業なら物ができあがる瞬間を”火花が散る瞬間”と喩えられているのですが、その火花が散る「現場」に近いところで働きたいという思いが強いです。そして、スターバックスの店長時代から人を育てることに大きなやりがいを感じていて、自分がマネージャーとしてチームを率いて、メンバーを育成するポジションであるかどうかの方が重要ですね。
◆chapter 2
日本から世界へ。
グローバル企業の本気に参画したい。
日本から世界へ。
グローバル企業の本気に参画したい。
・ではなぜ、トリドールホールディングスへ転職を決めたのでしょうか。
理由は大きく分けて2つあります。一つは日本発で海外に進出していく企業で働きたかったということ。これまでは海外のブランドや商品を日本に入れる仕事が中心でした。逆の立場で活躍してみたいと思っていました。そしてもう一つの理由はトリドールがグローバル企業として前進、成長していこうという並々ならぬ決意を感じたことです。
グローバルに展開して成功を収めたフードビジネスのほとんどが海外発の企業という事実は、スターバックスやマクドナルドなどで証明されていると思います。では日本企業はどうなのかというと一部の国や地域で成功したけれど、まだ大成功を収めている企業はないのではないかなと思います。そのような状況の中でトリドールの、本気で海外事業を成功させようとする意志に伸び代を感じまして、そこに自分が絡めることができたらきっと楽しいだろうな、と思ったのです。
・入社後は、どのようなプロジェクトへ参加されていましたか。
入社当時、香港の『譚仔三哥米線(タムジャイ サムゴー ミーシェン)』というライスヌードルの店舗を日本にオープンさせる計画が進行していました。私は海外店舗食品安全課の一員として、オープン前のトレーニングから参加しました。主にフードセーフティに関する教育や管理体制構築のサポートを担当したのですが、フードセーフティを実現するのに必要なトレーニングの「仕組み」が整っていないことに気づきました。マニュアル、手順書、チェックリストなどの他、新しいスタッフを迎え入れる体制や進捗の管理など、フードセーフティを実現するには欠かせない要素があります。それらを一つずつ、課のメンバーと一緒に作り上げました。日本の営業部の皆さんとだけではなく、香港の担当者ともミーテイングをもち議論しました。皆さんのおかげで基本的なコンテンツは揃ってきました。

・その後は、どのようなキャリアを重ねていったのでしょうか。
譚仔向けに作成したチェックリストやトレーニングのためのシナリオやツールを、プログラムとして仕組化していきました。ブランドの生まれた香港本国にも同様のツールはあるのですが、そのまま日本に持ってきても合致しない部分もありました。様々なツールを、トレーニングを受ける側の立場や、店舗の運営に忙しい店長の立場に立って、足りないものを補い、既にあるものはより使い勝手の良いものにブラシュアップしていきました。それを、国内の他のブランドや海外の丸亀製麵の店舗を担当されているメンバーに紹介する機会もいただきながら、イギリスやシンガポール、香港などの店舗において、フードセーフティの管理体制のみならず、オペレーションやトレーニングがどのように行われているかを見てまわりました。
そんな中で会社のミッション・ビジョン・スローガンを新しくすることとなり、企業として「感動(KANDO)体験を提供する」というキーワードが創出されました。これを実現するためには実行する人材である「KANDO Creators」を育成しなければならないということとなり、「KANDOリソース本部」、そして社内大学である「KANDO Creators大学」が新設。その際に私が以前につくったトレーニングプログラムが認められて、このチームを率いていくこととなったのです。「KANDO Creators」を育成するためのトレーニングプログラムやカリキュラムを構築していくのが私と新しいチームのミッションです。
◆chapter 3
失敗からも学びを得る。
その貪欲さが次への力となる。
失敗からも学びを得る。
その貪欲さが次への力となる。
・森さんの仕事へのこだわりは、いったいどこにあるのでしょうか。
私が大切にしているのは、「Think Globally, Act Locally」という考えです。グローバルに事業展開を行うにあたり、それぞれの国や地域にはそれぞれの文化や価値観、成熟度や優先順位がありますので、一方的にこちらから指示・教育するのではなく、それぞれとのバランスも考慮しなくてはなりません。現地のパートナー企業に対しては敬意を払い、バディとして同等の立場で一緒に働きたいと思いますが、こちらもホールディングスとして将来的なビジョンをもってパートナーを牽引し、様々な仕組みを提供していかなければならないと考えています。
あと、メンバーに対してはプロジェクトで作業を行う際、目的についてしつこいくらいに聞くようにしています。誰のために、何のために、どの方向を向いてやっているのかを聞くことで事の大切さを知り、本質的なところを大切にしてほしいと思っています。

・森さんにとって、トリドールホールディングスとはどんな会社ですか。
これまで経験した、違う会社でのやり方や文化を尊重してくれる会社だと思います。以前の会社の中には過去の事例を挙げて提案しても、「それはその会社だからできたことでしょ?」であっさり却下されるところもありました。ところが当社では「それ、どのようにやっていたの?」と興味をもって聞き返し、そこから自分たちの学びにしようとする姿勢を強く感じます。しかも成功だけではなく、失敗したことも興味をもって聞いてくる。私もそれに応え、過去の経験から新たな発見をすることで、今後の学びにしていきたいと思います。
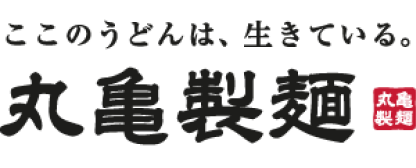

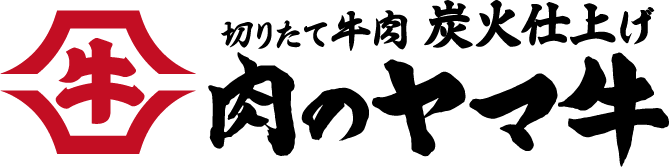
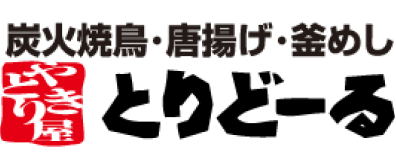
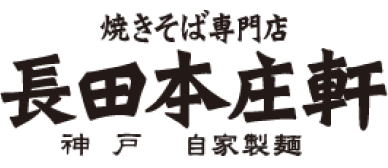

.png)

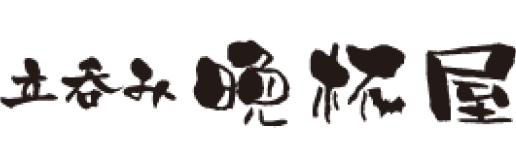
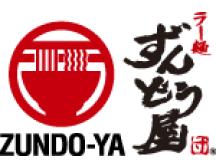
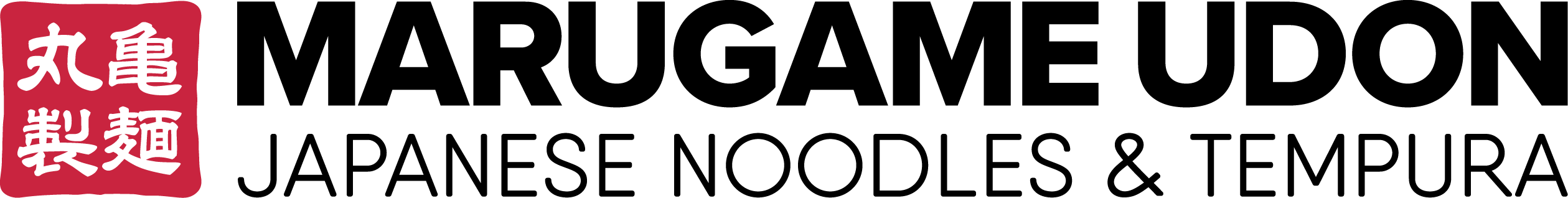
.png)