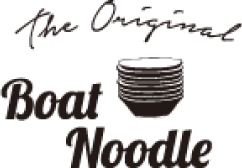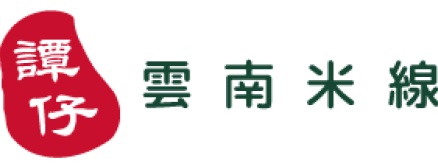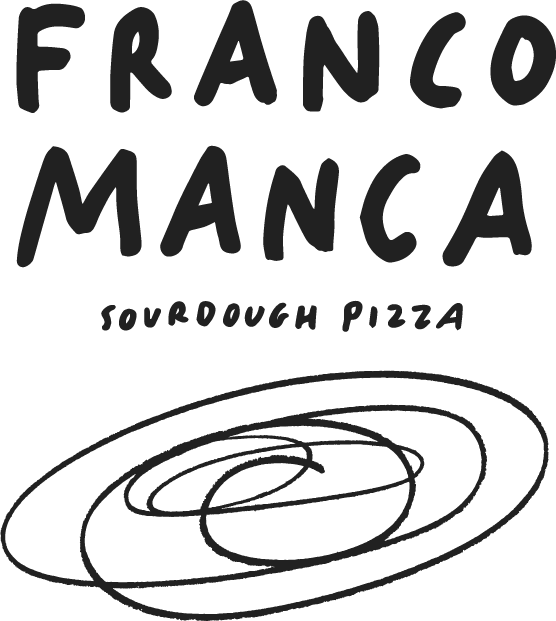トリドールグループは「手づくり・できたて」のおいしさをお客さまにお届けすることを大切にしています。いつも元気な声でお客さまをお出迎えする活気あるお店。従業員には知識や心構え、そして技術が重要ですが、パリッとしたきれいな白い制服も当社は大切にしています。
どうしても汚れや劣化してしまうこの制服を捨てずに、もっと大切にできないだろうか…。丸亀製麺では繊維リサイクルの中でも難易度の高い「制服から制服へ」のアップサイクルへの挑戦をスタートしました。
毎日の営業を、従業員とともに過ごした制服たち
「いらっしゃいませ!」
真っ白な制服を着た従業員が、元気な声でお客さまをお出迎えします。お客さまは当社の職人のような制服を見ると、改めて「丸亀製麺に来た」とお感じになっていただけるかと思います。
また店内調理にこだわった丸亀製麺では、従業員が店内で毎日粉から麺を打ち、出汁をとり、天ぷらの野菜切りや肉の加工調理など、さまざまな料理をしています。制服は、そういった調理シーンで衛生面を守っている存在でもあります。
日々の営業で、制服は従業員とともにあり、そして営業してきた月日を刻むように汚れは重なっていき、最後には捨てなければならない時を迎えます。
一緒に歩んできた制服たちを、捨てずにもっと大切にできないだろうか…。
廃棄ではなく有効活用によって、廃棄量削減と循環型経済への移行を目指したい。

この私たちの想いに、倉敷紡績株式会社(以下、クラボウ)と株式会社タイコーコーポレーション(以下、タイコーコーポレーション)が共感くださり、3社協働での制服アップサイクルの「つなぐ制服プロジェクト」がスタートしました。
使用済みの制服を、再び新しい制服にする難しさ
繊維製品のリサイクルでは、複数の原料が使われていることや、風合い・強度・機能性を維持することの難しさから同等製品へのリサイクルが困難とされています。
今回は、難易度の高い混紡素材の「制服」でのアップサイクルという難しい取り組みとなりました。
しかしこれまでも、クラボウとタイコーコーポレーションとは、厨房での汚れが付きにくく、落ちやすい清潔制服や熱中症対策のファン付き制服の開発に協働して取り組んできた実績がありました。
創業130年を超えるクラボウには独自の高い再資源化技術があり、タイコーコーポレーションは柔軟な企画・開発・製造力や、回収から供給までの丁寧な管理力があります。


「つなぐ制服プロジェクト」次々に集まる制服と、
そのバトンを協働パートナーへ
そのバトンを協働パートナーへ
いよいよ動き始めた「つなぐ制服プロジェクト」、回収エリアの効率性から西日本エリアの丸亀製麺の一部店舗が参加となりました。
店舗内での声掛けや控室での案内ポップ掲示などにより、一枚また一枚と制服が集まり、最後には多くの従業員がプロジェクトに加わり、本来は廃棄されていた上着やズボン、三角巾、前掛けといったさまざまな使用済みの制服が合計約1,600枚集まりました。
次にバトンはタイコーコーポレーションへ渡されます。これらの制服を丸亀製麺の各店舗と連携して回収。店舗側でもボタンやジップなどはカットしてはいますが、それでも見落としがあったものをタイコーコーポレーションが丁寧に除去します。

続いて、クラボウの工場へと制服リサイクルのバトンはつながれました。丸亀製麺の使用済み制服たちは、クラボウの独自技術により繊維原料として再資源化され、糸として紡がれ、織られ、染色・加工を経て布が完成します。これまでの新品の布と同等の品質になっているのか、何度も検証を行った上での調整を行っていきました。
こうして蘇った布は、再びタイコーコーポレーションに渡り、裁縫。最後には前掛けへと姿を変えました。

「つなぐ制服プロジェクト」のバトンは過去から未来へ
次々にバトンがつながれた制服たちは、最終的に約4,000枚の前掛けとなりました。
「おかえりなさい」
約1年の製造工程を経て、再びお店に戻ってきた前掛けたちは、現在従業員が着用し、お客様の目に触れる場所にて活躍しています。これまで一緒に過ごし、心がしみ込んだ制服たちが、また姿を変え、未来へと続いていく…。
「つなぐ制服プロジェクト」は、そういった想いのバトンも、過去から未来へとつないでいきました。
これからもトリドールグループは、限りある地球資源を大切にし、資源循環型社会の実現を目指した取り組みに挑戦していきます。
■クラボウ徳島工場
丸亀製麺では基本の制服類に関してはSDGsの観点で、クラボウ徳島工場で製造された布を採用しています。
クラボウ徳島工場は「SUSTAINABLE FACTORY」をテーマに、製造プロセスから環境負荷の取り組みを推進しています。例えば、水洗機改良による水の再利用や節水活動の徹底による排水量の削減、蒸気・排熱の回収利用や天然ガスへの燃料転換などによるCO2排出量の削減、焼却灰をセメント原料に再利用することなどによる廃棄物の削減に取り組んでいます。
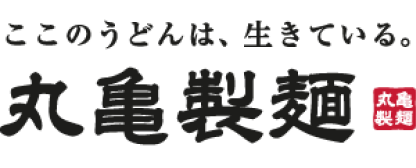

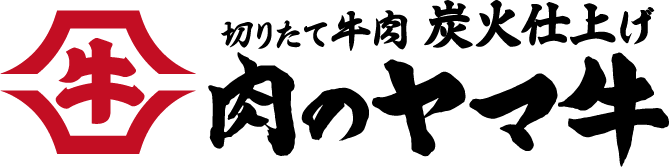
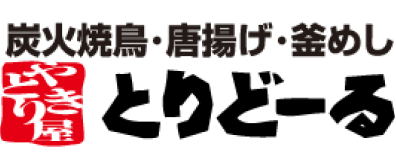
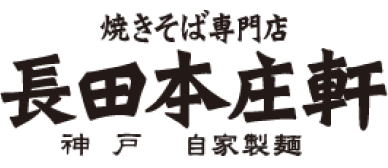

.png)

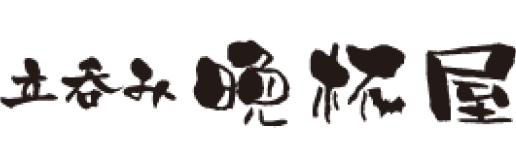
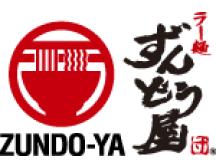
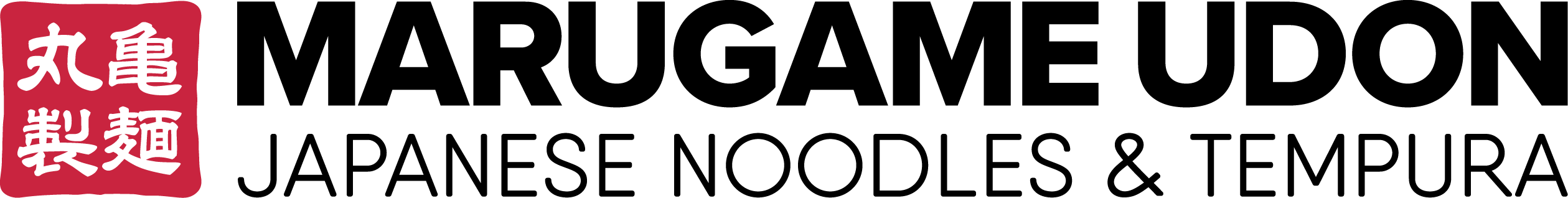
.png)